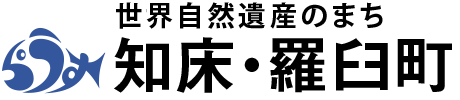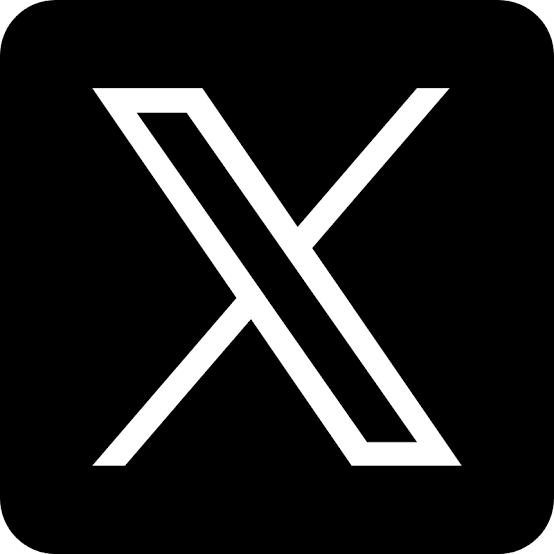国民年金について
国民年金の種類について
令和5年4月12日更新
平成14年4月から国民年金保険料は、直接国に納めることになりました。
年金制度は、老後の世代に年金を支給して経済的に援助する、世代間の支え合いの制度です。
また、老後だけでなく、事故や病気で障がい者になったとき、不幸にして生計を維持する配偶者を亡くして遺族になったときにも年金が支給される制度でもあります。
加入者は3種類
| 種 類 | 加 入 条 件 |
|---|---|
| 第1号被保険者 | 国民年金(20歳以上60歳未満の自営業者、農林漁業者、学生など)の加入者。 |
| 第2号被保険者 | 厚生年金(船員保険など)、共済組合の加入者。 |
| 第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人 |
希望で加入できる人
- 60歳以上65歳未満の人で受給資格のない人(昭和30年4月1日以前に生まれた人は70歳まで加入できます)や満額の年金を受けられない人。
- 厚生年金、共済年金などの老齢(退職)年金の受給者で60歳未満の人。
- 海外に在住している20歳以上65歳未満の人。
保険料の支払いのしかた
| 種 類 | 加 入 条 件 |
|---|---|
| 第1号被保険者 | 自分で国民年金保険料を納めなければなりません。 |
| 第2号被保険者 | 厚生年金保険料等は給料から天引きされます。 |
| 第3号被保険者 | 配偶者が勤務する事業主等を経由し、第3号被保険者の届け出により、保険料を納める必要はありません。配偶者の加入している年金制度全体が負担します。 |
【納付が困難なときは】
経済的な理由からどうしても保険料を納められない人は、「免除(全額・半額)制度」があります。
また、収入のない学生が社会人になってから学生期間中の保険料を後払いできる「学生納付特例」がありますので、ご相談下さい。
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。
20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金や厚生年金の加入期間等に応じて年金額が計算されます。
60歳から65歳までの間に繰上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や66歳から75歳まで※の間に繰下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」の制度があります。
※昭和27年4月1日以前生まれの方、または、平成29年3月31日以前に老齢基礎年金を受け取る権利が発生している方は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。
障害基礎年金
国民年金の加入者が病気やけがで障がい者になったときや、20歳前に障がい者になったときに受けられます。
障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
遺族基礎年金
国民年金の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が、遺族基礎年金を受け取ることができます。
「子」とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。
- 婚姻していない場合に限ります。
- 死亡当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。
第1号被保険者の独自給付
★付加年金(本人の希望)
月額400円の付加保険料を納めることにより、納めた月数×200円で計算した金額が老齢基礎年金に加算されます。
★寡婦(かふ)年金
老齢基礎年金の受給資格を満たしている夫が、年金を受けないで亡くなったとき、10年以上婚姻期間があった妻に60歳から65歳までの間支給されます。
年金額は、夫の受けることができた金額の4分の3の金額です。
★死亡一時金
保険料を3年以上納めた人が、年金を受けずに死亡したとき、生計を同一にしていたその遺族が遺族年金を受けられないときに支給されます。
ただし、寡婦年金を選択した場合は、支給されません。
税金がやすくなります
納めた保険料は、年末調整や確定申告のときに申告すると、全額が所得控除の対象になります。
国民年金の届け出をするとき
国民年金に関する主な届け出と、届け出に必要なものは次のとおりです。
届け出の際は、ご本人を確認できる「マイナンバーカード」等の身分証明書をご持参ください。
| 理 由 | 必要なもの |
|---|---|
| 20歳になったら | 事前に社会保険事務所から本人宛に資格取得届(申出)書が送られてきます。 直接返答するか、届いた書類と身分証明書を持参して役場へ提出してください。 |
| 厚生年金(船員保険など) ・共済組合に加入したとき、やめたとき |
年金手帳・基礎年金番号通知書、健康保険証(取得日や喪失日が確認もの)、身分証明書 |
| 厚生年金(船員保険など) ・共済組合の加入者の扶養になったとき、はずれたとき |
年金手帳・基礎年金番号通知書、健康保険証(扶養になった日を確認できるもの)、または、扶養からはずれた確認ができるもの、身分証明書 |
| 年金手帳・基礎年金番号通知書をなくしたとき |
身分証明書 ※令和4年4月より、20歳になったら年金手帳ではなく「基礎年金番号通知書」が交付されることとなりました |
| 受給の請求をするとき |
金融機関の通帳、年金手帳・基礎年金番号通知書、身分証明書 ※戸籍担当窓口で戸籍謄本を請求していただきます。必ず身分証明書をご持参ください。戸籍謄本は1通450円かかります。 |
| 死亡したとき |
請求者(亡くなった方の身内の方)の金融機関の通帳、年金手帳・基礎年金番号通知書、身分証明書、生計同一申立書(亡くなった方と同世帯ではない場合) ※戸籍担当窓口で戸籍謄本を請求していただきます。必ず身分証明書をご持参ください。戸籍謄本は1通450円かかります。 |
このページの更新日:2024年3月22日